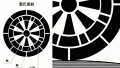炭治郎と禰豆子が変化するたび、月に模様が浮かびます。炭治郎は、月に痣のような模様が現れるたびに、スキルアップしていきます。
Demon Slayer Mark seems to have a deep connection with the moon.
鬼滅の刃の痣は、月と深い関わりがありそうです。
(この記事は、第1巻、4巻、7巻、8巻、10巻、12巻、13巻、14巻、15巻、16巻、17巻、18巻、20巻、21巻、22巻、23巻のネタバレを含みます)
「鬼滅の刃」では、全集中の呼吸を極めた者が一定の条件を満たすと、体に「痣」が現れます。その状態で発揮される基本的な力は、こんな感じ。
・傷の治りが異常に早い(第15巻128話)
・桁違いの反射、戦いへの適応、瀬戸際での爆発的な成長(第13巻114話)
ただ、戦国時代の始まりの呼吸の剣士たちが痣を発現したときと、大正時代の炭治郎たちが痣を発現したときでは少し様子が変わるようです。
第20巻176話の黒死牟のモノローグによると、さらにこんな力が発揮されているようです。
・胴を両断されても刀から手を離さない
・斬られても斬られても失血死しない
・鬼に匹敵する成長速度で、肉体の限界を超える動きをし続ける
・日の呼吸の使い手ではない者たちが刃を赤く染める
もちろん人間なので限界はあるようで、第18巻154話では、猗窩座に対峙する義勇さんの所でこんな解説が示されています。
全力疾走というものは、長時間できることではない。通常の人間は、全力であれば十秒走るのですら激しく息切れする。それ以上動き続けると、まず速度が落ち、技の精度も落ちていく。筋肉疲労で手足は鉛のように重くなる。疲労・負傷の概念がない鬼。さらには上弦との戦いで、長時間全力を維持し続けたのは、呼吸を使える者だけが起こせる奇跡だ(第18巻154話)
果たして、この痣とは一体なんでしょう?
第14巻の124話で、半天狗が生み出した憎珀天が、甘露寺さんの痣を見て「鬼の文様と似ている」とつぶやいていたように、実は下弦以上の鬼にも、体のどこかに文様があるんですよね。
つまり痣は、剣士の痣者と、下弦以上の鬼に見られるわけです。しかも似ている。
痣に関係する伝説が何かないかなと調べてみたところ、民俗学を研究している人の中に、月と痣の関係を挙げている人がいました。
月信仰と痣
月は表面に高低差から生じる影が見えます。民俗学では、これを「醜さ」や「不具」を象徴するとする地域もあります。
In Japan, it is said that the god of mountains and the god of fire also have ugliness and impairment, and there is a theory that the belief in the moon has an effect.
日本では、山の神や火の神も醜さや不具を持っていると伝えられていて、月信仰が影響しているとする説があります。
劉福徳という方の論文「蛭子考」では、月信仰と山の神、火の神の関係に触れています。
月の満ち欠けから「不具」を、月の表面に見える陰影から「醜さ」に関連させた物語が各地に残っているそうですよ。
さらに日本でも、山の神様は醜い容貌をした女性神と伝わることや、火の神様は不潔を嫌い、激しく祟るといった伝説も影響しあって、関連を持っていると考えられるようです。
大体、こんな感じになるのかな? 色分けして並べてみました。
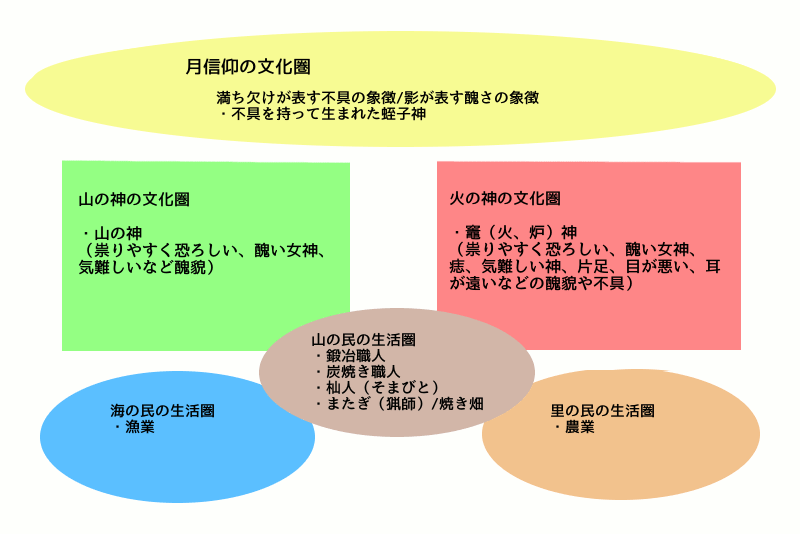
「鬼滅の刃」は、タイトルに「カグツチ」という名前が候補に入っていた(第1巻 3話末)というし、山岳信仰の関連が見られます。
上記の論文のように、山の神様も火の神様も月が持つ「不具」や「醜さ」からくる文化的な影響を受けているとしたら、「鬼滅の刃」で描かれる痣も、月が持つ痣のイメージに鍵がありそうです。
炭治郎や禰豆子は炭焼きの出身で山の民の生活圏に属しているし、最終決戦では無惨の毒で変貌した炭治郎の様子は、まさに月の不具や醜さを一身に背負っているみたいでしたもんね(汗)
そして、月といえば、管理人も気がついたことが一つあります。
刀鍛冶の里が鬼の襲撃を受ける第12巻。105話の最後のほうで描かれる月に、なんとも禍々しい痣のような模様が描かれているのです。そう思って見返してみると、時々このような月が描かれているみたいですよ。
では、月に浮かぶ痣のような模様、もしくはクレーターは、鬼滅の刃ではどんなときに描かれているんでしょう?
鬼の回想や過去の記憶の中に模様のある月が描かれるケースがあるのですが、物語の進行上で描かれている月に限ってまとめるとこんな感じになりました。
第1巻 お堂の月
最初、ここに描かれている月には模様はないなと思っていたのですが、かーなーり、薄っすらと模様がありますね。
お堂の上にかかっている月では、よくわからないのですが、崖の場面にも月が描かれていて、この月を拡大してみると模様らしいものが見えるかな? どうだろう。
この場面で描かれているのは…
禰豆子が最初に乗り越えた試練ですが、この時点の月の模様ははっきりしない描かれ方をしています。
第4巻 那田蜘蛛山の月
那田蜘蛛山の戦いでは、月が明るく輝き、痣のような模様が現れました。
第4巻29話で累が登場する場面では、月にはっきりとした模様が描かれます。そして、那田蜘蛛山の一件が解決するまで描かれる月すべてに、クレーターっぽい模様が描かれています。
この場面で描かれているのは…
・禰豆子は回復の眠りの中、お母さんに呼びかけられて目覚め、初めての血鬼術「爆血」を放つ
これまでも、手鬼の攻撃で気を失っている炭治郎に、弟の茂が呼びかけて危機を伝えることがありましたが、月に模様が描かれたこの場面から、明確なメッセージを含んで物語が急展開していきます。
第7巻 無限列車の月
無限列車のエピソードの表紙絵には、模様のある月が描かれています。
第7巻の話の中で月は出てきませんが、55話の表紙に描かれた無限列車の上空に、模様のある欠けた月が浮かんでいます。
この場面で描かれているのは…
この後、吉原・遊郭の話に入っていきますが、模様が描かれた月が出てくるのは話の展開では少し先のことになります。
第10巻 吉原・遊郭の月
妓夫太郎が登場する場面から、模様のある月が描かれています。
このエピソードでは、人間の限界を超えかけた炭治郎が堕姫をぎりぎりまで追い詰めたり、強い怒りのエネルギーで鬼化が進んだ禰豆子に痣が現れたりしますが、月が描かれることはありません。
妓夫太郎が登場する86話になってから、やっと模様の浮かんだ満月が現れます。ここから第11巻の97話まで、模様のある満月が空にありますよ。
この場面で描かれているのは…
・鬼の毒による負傷者の解毒に、禰豆子の爆血が力を発揮する
そして戦いの後、上弦の鬼に勝利した報告を受けて、「運命が変わり始める兆しだ」とお館様が予見する、その館の上にも模様の浮き出た月が浮かんでいます。
第12巻 刀鍛冶の里の月
玉壺が現れる直前に、模様のある月が描かれています。
第12巻の105話では、玉壺が現れる直前に、痣のようなくっきりとした模様が月に描かれています。ただ、模様のある月は、この一コマだけです。
この後もまだまだ鬼との戦いが続くし、空には月も描かれるのですが、すべて模様のないきれいな月に変わってしまいます。これまでのエピソードでは、その場面が終了するまで模様のある月が描かれていることが多かったのに、かなりあっさりしてますね。
第12巻の場面で描かれているのは…
・鬼と戦う中で、無一郎、甘露寺の二人に痣が現れる
・翌朝、禰豆子が太陽を克服する
この後、模様のある月が描かれるのは第15巻の131話で、珠世さんとお館様のカラスが接触する場面で模様のある月が描かれています。
第17巻 最終決戦の夜
最後に月に模様が描かれたのは、炭治郎が猗窩座と対峙し、禰豆子が人間に戻るために薬を飲んだ時でした。
そして最終決戦の夜、人間に戻る薬を服用した禰豆子を鱗滝さんが見守る場面(147話)で、館の上に模様のある月が描かれています。このとき炭治郎は、ちょうど猗窩座と対峙する場面。
月に模様が描かれるのは、これが最後になります。
第17巻で出てくるのは…
・炭治郎、父に教えてもらった透き通る世界を体得
この後は無限城での戦闘が続くので、月はしばらく描かれないのですが、無限城が地上へ表れる第21巻 183話で描かれる月には、痣のような模様はなくなっています。
このときも、刀鍛冶の里と同じくあっさりした感じの現れ方でした。
鬼の痣
こうして通して見ていくと、月に痣のような模様が現れるたびに、炭治郎と禰豆子は変化していきます。
鬼を倒すために必要なヒノカミ神楽(日の呼吸)を技として自分のものにし、痣を出現させて加速させ、赫刀を手に入れます。
でも、第20巻175話で縁壱が言っていたように、「これから生まれてくる子供たちが、(今の世代を超えた)さらなる高みへ登っていく」というように、ゆっくり進むのが自然の理なら、第20巻170話で黒死牟が言うように、その世代のうちに問題を解決しようとして、「痣を出現させ、力を向上できたとしても、所詮それは寿命の前借りに過ぎない」ことになるのでしょう。
猗窩座と対峙して痣を出現させた義勇さんによると、「(圧倒される強者と出会って)閉じていた感覚が叩き起こされ、引きずられる。強者の立つ場所へ」(第17巻150話)と言っているので、痣の発現はかなり無理がかかるようです。
そんな痣ですが、鬼を倒すために働いてくれているように見えるのに、鬼にも痣があるのは何なのでしょう?
人間の側から見れば、人を助けているように見えますが、陰陽五行に出てくる比和(ひわ)の関係のことを考えると、いいも悪いもなく影響しあうように、人も鬼も関係なく、そこに存在していれば、月の影響は痣となって現れるのかもしれませんね。
ちなみに「角川 漢和中辞典」によると、「痣」は病垂れに志(あとがつく)と書きます。
「志」の字義はこんな感じ。「志」は「幕末の志士」とか「少年よ大志を抱け」みたいなイメージが強い文字ですが、何かを記録したり残したりする意味もあるみたいですよ。
1. こころざす。心をその方にむける。こころざし。
2. のぞみ。ねがい。
3. したう
4. しるす(記)。かきしるす(誌)。しるしたもの。書きもの。記録。
5. おぼえる
ワニ先生、この辺の痣の意味もわかったうえで、わざわざ痣に設定してるんでしょうか…?
ちなみに英語では、痣のことは”mark”とか”Demon Slayer mark”と訳されているようです。4番のイメージに近い感じかな?
尋常でない力を持つ鬼と、人並み外れた力を持つ痣者、それぞれ月の影響が現れた印として描かれているのが、鬼滅の刃の痣なのかもしれません。
当ブログには「痣」に関して考察している記事が他にもあるので、よかったらこちらも覗いてみてくださいね。