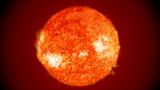富士山の赫夜姫伝説は、「鬼滅の刃」の「かくしゃくのこ(赫灼の子)」と関係がありそうです。
(この記事は、1巻、2巻、12巻、15巻、20巻、21巻、23巻のネタバレを含みます)
炭治郎のことを「赫勺の子」と呼んだのは、炭治郎に日輪刀を届けてくれた鋼鐵塚さんでした。
火仕事をする家では、「頭の毛と目ん玉が赤みがかっている」(2巻 第9話)、そういう子が生まれると縁起がいいと喜ぶのだそう。
でも、「赫灼の子」って何のことでしょう?
「縁起がいいなあ」という言葉が意味するもの
赫灼の子の特徴は「赤みがかった髪」に「赤みがかった目」ですが、「鬼滅の刃」には同じ特徴を持った人がいますよね。
20巻の表紙を見るとわかりますが、無惨を追い詰めた「最初の呼吸の剣士」と呼ばれる縁壱も同じ特徴を持っています。
では彼のように、無惨を倒せそうだから縁起がいいのでしょうか?
でもそれなら、「赫勺の子が救ってくれる」といった言い方になりそうですよね。
「縁起がいい」というのは、経験的に感じてきた「いい兆しや前兆があらわれる」ことなので、これまでに何度も起こってきたことや、何か信じていることに沿った話になるはずです。
鋼鐵塚さんは鍛冶職人なので、製鉄の文化で何か言い伝えがあるのかもしれません。
「赫」の字を名前に持つ女神
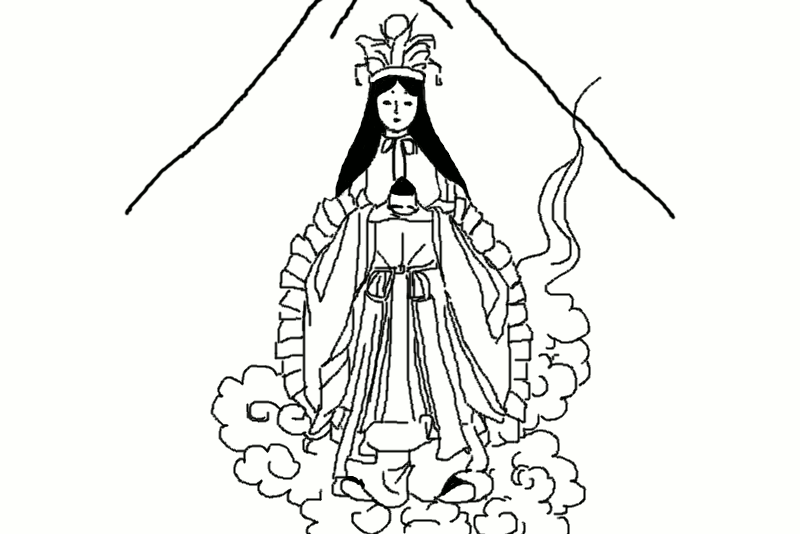
富士山に伝わるかぐや姫は、富士山の化身とされています。
It was full of light that illuminates the surroundings brightly even at night, so it was named Kaguyahime(赫夜姫 Kaguyahime) in the sense that it is a princess who shines brightly at night.
夜でも周りを明るく照らす光に満ちていたので、夜に明るく耀く姫という意味で「赫夜姫」と名付けられました。
Mt. Fuji was thought to be the same as Dainichi Nyorai, but it was also thought that there was also the appearance of the Asama Bodhisattva.
富士山は大日如来と考えられていましたが、浅間大菩薩の姿もあると考えられていました。
ということで調べてみたところ、名前に「赫」の字を持つ方を見つけました。それは、「かぐや姫」。
一般的には竹取物語の「なよ竹のかくや姫」が有名なので「かぐや姫」と平仮名で書くことが多いですが、富士山に伝わる伝説では「赫夜姫」と漢字で表記されて、伝わる話も少し違っているのです。
赫夜姫は、富士山の御神体の化身
夜でも昼間のように明るく、神々しい光を放っていたから「赫夜姫」と呼ばれるのですが、赫夜姫は月へは帰りません。夜に輝くといえばお月様の印象があるのに。
伝説では富士山のご神体の化身が赫夜姫で、世の中の人々を救うために浅間大菩薩(せんげんだいぼさつ)という神様となって、この世に現れたとされているのです。上の絵のような感じの神様になるようです。
浅間信仰によると、浅間大菩薩は大山祇命(オオヤマツミノミコト)の娘で、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の后でもある神様とされています。
大山祇命は、古事記では「大山津見神」(オホヤマツミノカミ)のこと。そして瓊瓊杵尊は「天邇岐志国邇岐志天津日高日子番能邇々芸命」(アメニキシクニニキシ アマツヒタカヒコホノ ニニギノミコト)のこと。つまり、浅間大菩薩は古事記では「木花之佐久夜毘売」(コノハナノサクヤビメ)のことになるみたいです。
さらに富士山の山頂には江戸時代まで、浅間大菩薩の本地仏(ほんじぶつ)として大日如来を安置する大日堂があったそうですよ。
本地仏というのは、鱗滝さんのキツネ面を調べていたときに出てきた、稲荷神にもありましたよね。神仏習合で使われる言葉でした。
本地垂迹(ほんじすいじゃく)という、仏や菩薩が衆生を仏道で救うため、借りに日本の神々の姿となって現れるという考え方に出てくる言葉です。
本地仏は、姿を借りる前の本来の仏や菩薩のことをいいます。
この考え方は明治初期の神仏分離令以降、衰退してしまいます。
「本地垂迹」から見える赫灼の子
密教では他の神仏はもちろん、世の中のすべてのものが大日如来から生まれたと考えられていて、大日如来の「大日」は、「大いなる日輪」を意味します。
つまり、太陽の象徴である大日如来の垂迹が浅間大菩薩で、その化身の女性に月を暗示させる赫夜姫という名前が付けられていたということになるんですね。
もしも、この赫夜姫の申し子のようだということで、「赫勺の子」と呼ばれているのだとしたら、太陽と月の両方の要素を持つことになります。
ヒノカミ神楽を継承して、重要な場面になるたびに月に痣のような模様が描かれる炭治郎にぴったりのイメージですよね。
上記記事では炭治郎の場面を中心に見ていますが、実は縁壱も、兄巌勝と再会した夜や、奥さんの ”うた”が鬼に襲われる夜など、重要な場面では月に痣のような模様が描かれています(20巻 第174話、第176話、21巻 第186話)
「鬼滅の刃」って、月の表現に注目して読み返してみると、ちょっとおもしろいところがありますよ。
赫夜姫伝説を伝える人たち
奥多摩地方は修験道の盛んな山が多くありました。炭治郎や伊之助の住んでいた山も、修験道の霊山です。
Mt. Fuji, where the legend of Princess Kaguya is located, was also a mountain of Shugendo.
かぐや姫伝説がある富士山も、修験道の山でした。
In folklore, some people think that Shugendo and the people of the steelmaking group had a deep exchange.
民俗学では、修験道と製鉄集団の人々は深い交流があったと考えている人がいます。
富士山の祭神・守護神が女神として成立していったのは、富士修験(村山修験)を中心とした富士山信仰が深く関係しています。
室町時代から戦国時代にかけて隆盛を誇りましたが、その後は大流行した富士講にまとまっていき、富士修験道としては現在はその遺構が残るのみとなっています。
「吾妻鏡」に伝えられる「富士の人穴(ひとあな)」にあらわれたという、浅間大菩薩につながる富士信仰を支えたシステムです。
富士山に集団で登拝するのを主な目的とする団体で、講の皆でお金を出し合い、代表者が富士登山を目指します。富士山に直接登れない人には、各地に富士山に見立てた富士塚が造られました。
流行病が蔓延する際には、仙元大菩薩(せんげんだいぼさつ)より授かったとする「富世貴」(ふせぎ)という呪符を人々に配って評判になっていたようです。
江戸八百八町に八百八講と称されるほど信仰を集めていました。
富士講に関係の深い角行は、禰豆子に重なるイメージがありそうですよ。⇒煉獄さんが無限列車に乗車することは決まってた? 姫路の奇祭に重なる「鬼滅の刃」
赫夜姫伝説に深く関わる修験道の文化
ブログ「富士おさんぽ見聞録」に詳しいのですが、ざっくりまとめると、戦国時代は今川氏などの権力者から庇護を受けていた富士修験ですが、江戸時代に入るとその勢いにも陰りが見られるようになります。
江戸中期になると、噴火・台風・地震といった自然災害が重なって、宗教施設に大打撃を被ってさらに衰退。諸国へ人を派遣して布教活動に力を入れていた時期があります。
江戸末期には社殿を再建するなど、回復を見せるのですが、明治の神仏分離と修験道の禁止により大きく荒廃してしまいます。
さらに明治39年になると、本拠地となる村山を経由しない新しい登山道が開設されたことで、旧道は廃道に追い込まれてしまいました。
道が変わるということは、人の流れが変わるということ。人の流れが途絶えた村山修験の地は、歴史からも忘れ去られてしまったようです。
炭治郎たちの住む山も、修験道の文化圏
「鬼滅の刃」の時代には富士修験も寂れていたと思いますが、それでもこうした修験道の記憶を伝える人はまだいたかもしれません。
「修験道と製鉄集団は山中の鉱脈情報を介して深いつながりを持っていた」と考える人もいるので、赫夜姫の話を鋼鐵塚さんたちが知っていても不思議ではないんですよね。
地図で確認すると、富士山は炭治郎たちの住む山に意外と近いのです。どちらも修験道が盛んだった山なので、文化圏としてはお隣と言ってもよさそうです。

宝満山と英彦山にもあった刀鍛冶文化
調べてみると、ワニ先生の地元の福岡にも、宝満山(ほうまんざん)と英彦山(ひこさん)に修験道の文化があり、両山を両界曼荼羅(りょうかいまんだら)に見立てて「入峰」(にゅうぶ)という入山修行が行われていました。
曼荼羅は「仏法の本質を象徴するもの」という意味のサンスクリット語の音訳で、密教の世界の仏様を図形に表して、視覚的に理解できるように表現したものです。
両界曼荼羅は、「金剛頂経」(こんごうちょうぎょう)を表す金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)と、「大日経」(だいにちきょう)を表す胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)で構成されていて、どちらも大日如来を表しています。
この曼荼羅は、9人の柱と12鬼月の秘密が隠れていそうですよ。⇒9人の柱と12鬼月の謎を解く鍵は、平等院にあり
興味深いのは、九州は古くから大陸の窓口だったため、国防の面でも重要な場所として、かなり古くから刀鍛冶文化があったようです。宝満山と英彦山にあった修験道の文化圏に、刀鍛冶文化が重なっているんですね。
竈門山(宝満山)には「金剛兵衛盛高」(こんごうびょうえ もりたか)という刀鍛冶が、そして英彦山には「左文字」(さもんじ)の祖といわれる「良西」(りょうさい)という刀鍛冶が住んでいました。
それぞれ修験者として僧籍も持っている刀鍛冶だったようです。
後醍醐天皇と足利氏の間で発生した建武の乱(建武2年~建武3年、1335~1336年)では、左文字派の人々は南朝方に属する菊池武敏(きくちたけとし)に従って戦っているのですが、時の利がなく菊池軍は大敗。左文字派で生き残った者は散り散りになって、各地に移住していったそうです。
この展開、匂いますよね(笑)
参考 英彦山と修験者を訪ねて(前編) | 武士道美術館
参考 英彦山と修験者を訪ねて(後編) | 武士道美術館
参考 五箇伝以外の代表的な名工 左文字 | 刀剣ワールド
伝説の名刀「蛍丸」につながるもの
北九州で起こったこのときの戦は「多々良浜の戦い」(建武3、1336年3月)といって、阿蘇大宮司 阿蘇惟澄(あそだいぐうじ あそこれずみ)が用いた4尺5寸(約1m36cm)の大太刀も、刀の刃がノコギリのようになってしまうほどの激戦だったそうです。
ノコギリのような刃毀れをした刀 ── まるで伊之助の刀のようです。
しかもこの刀には、不思議な伝説が残っています。
その夜、惟澄が見た夢の中で、刃毀れした欠片が無数の蛍になって元の刀に宿り、刃こぼれのない刀に戻ったというのです。惟澄が目を覚ますと、実際に刃毀れが直っていたため、この大太刀は「蛍丸」と名付けられました。
蛍といえば、鋼鐵塚さんの名前が蛍です(12巻 第101話)。
刃毀れを直してくれた夢の中の「蛍」と、炭治郎の刀を打ち直してくれる「鋼鐵塚蛍」さん、蛍で一致しています。
「鬼滅の刃」には、刀鍛冶文化と修験道文化が、つながっていてもおかしくない設定が揃っているようです。
参考 05多々良浜の戦い | 菊池一族
参考 武将 惟澄と蛍丸に捧げる 純米吟醸 蛍丸 | 通潤
参考 菊池一族、九州を翔ける③・・・・菊池武敏、多々良浜に舞う| エンクレスト歴史探訪
「赫」が持つ色はかなり広範囲
赤色は太陽を表す色です。中国の古い書物には、太陽は火が集まったものだと説明されています。
In Demon Slayer, Those who use fire will be delighted when Kakusyakunoko is born. Maybe it’s because it represents the sun, which is a collection of fire.
「鬼滅の刃」では、赫灼の子が生まれると火を扱う仕事の人が喜ぶのは、火の集積である太陽を表しているからかもしれません。
赫灼の子が持つ色に注目してみると、赫灼の「赫」の字は「赤」を2つ並べることで、火が真っ赤にかがやくことを意味を表しています。
角川 漢和中辞典の「字義」には、こんな意味が説明されていました。
・あかい(-し)。まっか。赤色が濃いこと。
・かがやく。ひかる。きらきらする。
・明らかなこと。また、勢いが盛んなこと。
・怒りを発するありさま。
・おどす。しかる。
「赫」は光のかがやきだけでなく、赤い色も表しているんですね。
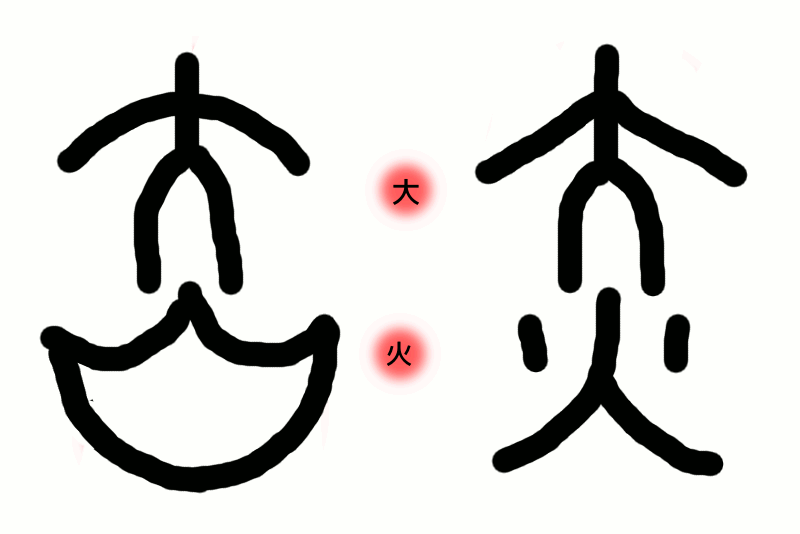
さらに「赤」の文字を調べてみると、古い字形は「大」と「火」から成る文字で、上の図の左のように「火」を図形のように表したり、右のように「火」の文字が書かれたりしていたようです。
火がかがやく(赫)と大いに燃えることから、火の「色」や、明るく輝く「あか」の意を表すわけですね。
「参考」の部分を見ると、こんな感じ。いろいろな赤を包み込んだ色が「あか」になるみたいです。
「あかい」の同訓は赤・紅・朱・丹・緋・赭。
「あかい」の同訓となる色が具体的にどんな色になるのかというと、こんな感じ。「あか」と言われて普通にイメージする赤色から茶色に近い色まで含まれています。
| 色見本 | 表記と読み | 意味 |
 |
赤(あか) | あかい色の総称で、あかの正色といわれる |
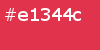 |
紅(べに) | べにばなの色で、桃色がかったあか |
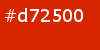 |
朱(しゅ) | 朱砂の色で、あかの濃い色 |
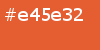 |
丹(たん) | 丹砂の色で、朱の白色をおびた色 |
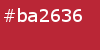 |
緋(ひ) | 紅色の濃い色 |
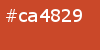 |
赭(しゃ) | べんがら色、赤土のいろ |
火仕事をする家が「赫」を「縁起がいい」と喜ぶ理由
民俗学では、村武精一という方が「南島文化では,赤が男性神で太陽を,黒は女性神で月の表象を持っている」と指摘しているそうで、赤は太陽を表す色でもあるようです。
日本の神社でも晴天祈願に白馬(もしくは赤馬)が、降雨祈願には黒馬が絵馬に描かれるので、重なるところがありますよね。
参考 色のフォークロア研究における諸前提 小林忠雄 | 国立歴史民俗博物館学術情報リポジトリ
「鬼滅の刃」でも日輪刀に「猩々緋」という「赤」が使われていますが、そうした破邪除災としての色の他に、お正月のお祝いに使う「赤」のように、日常を表す「褻」(ケ)に対して非日常を表す「晴」(ハレ)の色もあります。
お正月のお祝いに赤い色を使うのは、邪気を払い、めでたい兆しを表す吉祥としての色です。
こういうことから言うと、炭治郎のように赤みがかった目や髪のことも、「太陽に通じる=縁起がいい」と感じるのは自然なことなのかも。
しかも太陽は、「『山の神』易・五行と日本の原始蛇信仰」(吉野裕子著)によると、「日、即ち太陽は火精、つまり火の集積である。」と「五経通議」に解説されているそうで、こうした意味があるなら、火仕事をする皆さんが「太陽に通じるものが喜ばしい」と感じるのもわかる気がします。
赫灼の子が実在するのかどうかまではわかりませんでしたが(汗)伝説の中には赫灼の子がどんなものなのか、理解するためのキーワードがけっこう揃っているみたいです。
鬼化した禰豆子も、実は赫灼の子かもしれない
そして、瞳の色が淡紅色、髪の毛先がべんがら色、もしくは丹色をしている禰豆子も、この「あか」の特徴を持っていることがわかります。
人間のときの禰豆子は黒髪だったので、鬼化することで赫灼の子の特徴を持つことになったみたいですよ(1巻 第1話)
目の色は「紅」で、髪の毛先の色は「丹」とか「朱」、「赭」の色に見えることもあります。
原作では白黒なのでわかりにくいですが、アニメ版では鬼化した直後に変わっているのがわかります。
だとすると、炭治郎も禰豆子も、鬼化しても最終的に太陽を克服してしまうのは、二人とも赫夜姫伝説からつながる太陽の要素を持った赫灼の子だったからと言えるのかも。(15巻 第126話、23巻 第201話)
無惨様も巌勝ではなく、赫灼の子の要素を持った縁壱のほうを鬼にしていれば、太陽を克服するのもあっという間だったわけです(20巻 第187話)
判断を間違えちゃいましたね。
あ、でも、その前に日の呼吸で斬られてしまいますか(汗)
ちなみに、禰豆子の太陽克服に関しては、日本神話を織り込んだ表現があるようです。当ブログには他にも炭治郎に関する考察記事もあるので、よかったらこちらも覗いてみてくださいね。