
禰豆子は鬼になってから、毛先がベンガラ色で淡紅色の瞳に変わりました。
It has the element of the “Kakushaku no ko”, but the color of the eyes could also mean rabbit.
赫灼の子の要素もありますが、目の色はうさぎの意味もありそうです。
Rabbits are known as sleeping animals and are a symbol that connects with the mountain god.
ウサギはよく寝る動物として知られていて、山の神ともつながるシンボルです。
(この記事は、第2巻、第7巻、第8巻、第9巻、第10巻、第12巻、第13巻、第15巻のネタバレを含みます)
炭治郎には、「火之迦具土神」(ホノカグツチノカミ)を祀る愛宕神社と重なるイメージがいくつもありました。
それでは、禰豆子はどうでしょう? やっぱり火之迦具土神と重なるのでしょうか?
火の神様「カグツチ」と禰豆子
禰豆子といえば、自分の血を使った血鬼術「爆血」があります。(第5巻 40話)
「燃える血、爆ぜる異能」は人間には害をなさないけれど、鬼や鬼の血鬼術には威力を発揮する不思議な炎。まるで、神である伊邪那美命を傷つけてしまった、火之迦具土神の炎のようです。
そして、敵を攻撃するときに見せる強力な蹴りがあります。
蹴りといえば、日本書紀に出てくる野見宿禰(ノミノスクネ)という人がいますよね。天穂日命(アマノホヒノミコト)の子孫と伝わる出雲の人で、日本の相撲の起源とも言われる人物です。
ちなみに、天穂日命というのは、天照大御神(アマテラスオオミカミ)と建速須佐之男命(タケハヤスサノオ)が誓約を交わしたときに、天照大御神の勾玉から生まれたとされる五柱のうちの一柱の神様のことです。
「禰」の字が禰豆子と似ていますが、「宿禰」は武人や行政官を表す古代日本の称号なので、特に何か名前が関係するというわけではなさそうですが。
ともあれ、野見宿禰は剛力無双の人で、垂仁天皇(スイニンテンノウ)の召により、当麻蹴速(タイマノケハヤ)と力比べを行って勝利するのですが、その極め技がかなりすごいのです。
二人相對立 各擧足相蹶 則蹶折當麻蹶速之脇骨 亦蹈折其腰而殺之
向かい合って立った2人は、お互いに足をあげて蹴り合い、当麻蹴速の脇骨を蹴り折り、さらに腰の骨を踏み折ってこれを殺した。
蹴り技で相手が死んでしまっていますよ(汗)
当麻蹴速という人は自分の力を過信して、「自分に勝てるものはこの世にいない、誰か自分と勝負できる者はいないのか」と豪語していたような人だったので、己で招いた災難だったみたいですが、原始的な相撲はこんな感じで、荒々しい格闘技だったみたいです。
この他、古事記には、国譲りの第3の使者として派遣された建御雷神(タケミカズチノカミ)も、大国主の子である建御名方神(タケミナカタノカミ)と相撲をとって勝利しています。
建御雷神は火之迦具土と直接関係のある神様で、火之迦具土が首を切り落とされたとき、十拳剣の根本から滴り落ちた血から生まれた八柱の神様のうちの一柱でした。
このように、火之迦具土が属している日本の神話には、蹴り技を使う相撲が普通に出てくるようで、禰豆子の蹴りもこういうところと重なっているのかもしれませんね。
子守唄のウサギと山の神
そして、禰豆子のもう一つの大きな特徴は「眠る」ことです。通常の鬼が人を食べることで力の消耗から回復したり、より一層その強さを増すところを、禰豆子は眠ることで回復します。(第2巻 10話)
禰豆子がよく眠るのは、ご先祖のすやこさんがよく寝る人だったこともあるみたいですが(第12巻 99話、第13巻 112話末)
第10巻 85話に出てくる子守唄にもヒントがありそうです。
こんこん小山の子うさぎは
なぁぜにお耳が長うござる小さい時に母さまが
長い木の葉を食べたゆえ
そーれでお耳が長うござるこんこん小山の子うさぎは
なぁぜにお目々が赤うござる小さい時に母さまが
赤い木の実を食べたゆえ
そーれでお目々が赤うござる
子守唄にウサギが登場するのは全国的に多数存在するのですが、鬼滅の刃 に出てくるこの歌は、佐賀県に伝わる子守唄になります。
そして、こうした子守唄に出てくるウサギは、ただかわいいだけではなく、信仰に関わる象徴と見ることができるみたいですよ。
魂鎮め(たましずめ)のための子守唄
「ウサギの神性について」という論文では、ウサギは月の神、氏神、祖霊、農神、族霊と関連してとらえられる地域があることから、「ウサギを山の神や産神として信仰する世界があった」と指摘しています。
参考 ウサギの神性について “The Divinity of Usagi,the Hare” 赤田光男 | 日本の論文をさがす CiNii Articles
ウサギが山の神と同一視された要素として、山の神が12人の子供を持つことと、ウサギは多産で繁殖力に富んでいることが重なるみたいです。「山の神様が12人の子供を生む」という話は、テレビの昔話にもありましたよね。
山の神とウサギを一体的にとらえることで、論文では「ウサギを子育ての守護神」とみなしているのですが、ここに「眠り」のキーワードが出てきます。
「兎と亀」の昔話にあるように、ウサギは長い昼寝をする生き物なので、子守唄には「ウサギのように眠りについてもらいたい」という子守の願いが込められているというんですね。
ウサギの睡眠時間は平均8時間。そんなに極端に長いわけではありませんが、寝たり起きたりを細かく繰り返すので、ウサギを飼っていると寝ている姿をよく目にするようです。特に換毛期のウサギは体力を使うのか、いつもよりよく眠る姿を目にするみたいですよ。
上記論文によると、ぐずついて泣く子は「霊魂が遊離している」とみなせるので、子守唄を歌うことは霊魂を元の体に入れるための行為となるそうです。
眠りを象徴するウサギを子守唄に込めることは、子供の鎮魂と心の発展のための大切な存在として、祈りにも似た意味が込められているんですね。
ウサギのイメージと重なる禰豆子
でも、そういえば、禰豆子とウサギを関連付ける人はすでにいましたよ。第7巻 55話の無限列車で、伊之助の夢に出てきた禰豆子はウサギの耳をつけていました。
珠世様によると、禰豆子は「自我を取り戻さず」「幼子のような状態でいる」(第15巻 127話)と見ていますが、頭をぐいぐい寄せてくる「なでてアピール」は、確かにウサギです。禰豆子は山の神様と同一視されるウサギに見立てられていることは確かなようです。
そういえば、「山の神の文化」は火山つながりで「火の神の文化」とも近い関係にあります。当ブログでも別記事にまとめていますが、それぞれ月信仰の影響を受けていると指摘する論文もありました。
これで見ると、炭治郎と禰豆子はそれぞれが火之迦具土に重なる存在だとして、炭治郎はその中でも「火の神の文化」が色濃く表現されていて、禰豆子は「山の神の文化」が色濃く表現されていると言えそうです。
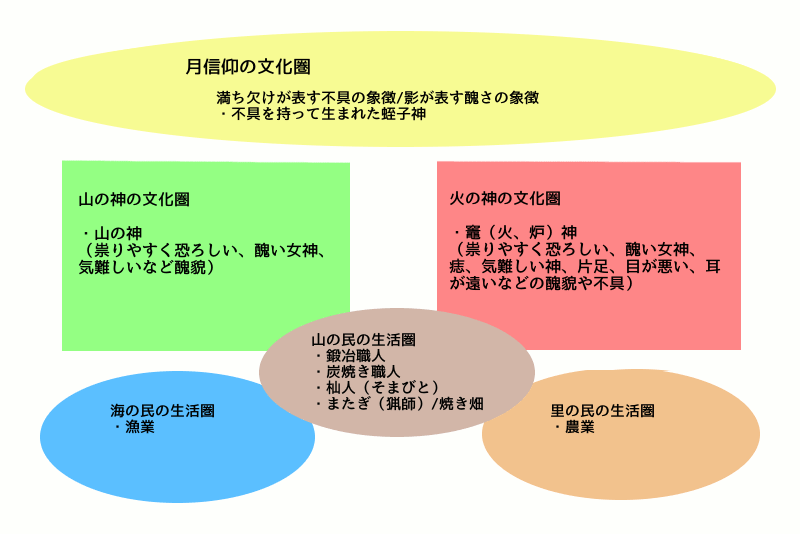
禰豆子の名前からわかること
禰豆子の名前も、使われている漢字から見ると興味深いですよ。
「角川 漢和中辞典」によると、「禰」の字は、「祖先の廟に新しく加えた神の意味。先祖のうち、一番新しく祀られた神は父であるところから、死んだ父の意となり、また、父をまつった廟の意味となった」のだそう。
字の意味も、「みたまや、おたまや」となるようです。
1. 父のおたまや。父の廟。
2. 廟にまつった父の称。
3. 戦争のとき奉持していく位牌。かたしろ。
「みたまや」もしくは「おたまや」は、貴人の霊を祀ってある所とか、霊廟 (れいびょう) のことになります。
「月の神=ウサギ」と見たときに重なる、「氏神」、「祖霊」、「農神」、「族霊」といったイメージにつながる漢字が使われていると言えそうです。
そして禰豆子は、昼間は鱗滝さんが作ってくれた箱に入って、炭治郎に背負われて移動するのですが、これはまるで行脚僧や修験者が背負っている「笈」(おい)のようにも見えます。
笈というのは、仏像、仏具、経巻、衣類などを入れて、行脚僧や修験者などが背負って歩く道具箱のこと。
「おたまや」を意味する文字を名前に持ち、氏神や祖霊、族霊と関係のあるウサギに重ねた禰豆子を箱に入れて、修験者のように背負って歩く炭治郎の姿は、ヒノカミ神楽を継承して戦いの場で実践していく者としてぴったりのイメージですよね。
この姿は山伏の姿にも似ていて、大江山の鬼退治に山伏姿で向かう源頼光一行の姿とも重なっているところが興味深いです。
適確なアドバイスは、「音柱」だから?
ところで、暴走する禰豆子に炭治郎が子守唄を歌ってやる前に、「子守唄でも歌ってやれ」とアドバイスをするのは音柱の宇髄さんでした(第10巻 85話)
もしかすると宇髄さん、「魂鎮め」という子守唄の効果をわかったうえでアドバイスしている可能性があります。
なぜなら、彼は音柱だから。
「水と祭祀の考古学」(奈良県立橿原考古学研究所付属博物館編)によると、鎮魂祭(みたましずめ)では「音」が使われるというんですね。
古来、人間は魂魄(こんぱく)からなっていると考えられていました。
ざっくり言って、「魂」は精神で「魄」は肉体です。この二つが分離すると、人間は死んでしまいます。
これを防ぐために鎮魂祭(みたましずめ)が行われるのですが、この時に行われる儀式が衰えた魂を力づけるために行う「魂振り」(たまふり)です。
・体を揺する
・強烈なリズムを聞かせる
・花見をする(花が持つエネルギーを体内に取り入れる)
・山見をする(青葉、わかばの生気を体内に取り入れる)
・弦楽器を弾奏する
など
解説の中で例として挙げられていたのが、毎年、十一月中寅日(しもつきのなかのとらのひ)に宮中で行われる冬至の行事の一つ「鎮魂祭」なのですが、こんなふうに紹介されています。
冬至は昼が短くて夜が長い日であり、太陽も地上も生気をなくす時期です。このときに合わせて鎮魂祭を行い、天皇の生気を復活するのが趣旨です。
儀式の次第は神座に天皇の御服の筥(箱)を用意し、琴の弾奏に合わせて逆さに伏せた宇気槽を御巫(かんなぎ)が矛(さなぎ)で十度撞くごとに木綿の糸を結ぶと共に、開いた天皇の御服の筥をゆっくりとゆすります(『儀式』巻第五「鎮魂祭儀」)
槽は液体などの容器で、逆さに伏せた空の槽を矛で撞くと大きく響きます。また、服は天皇の形代ですので、これに琴や宇気槽の響く音で活力を与え、間接的に天皇の魂振りをするのです。
はこ。中国上古(伝説上の帝王・伏羲の時代)、農作物の量をはかる単位。
槽(うけ)と同じ。上代の祭具。中がうつろな桶のようなものと考えられています。穀物貯蔵用のおけとも。
記紀(古事記、日本書紀)に出てくる天の岩戸伝説では、天之鈿女命(アメノウズメノミコト、古事記では天宇受売命)が覆槽(古事記では汙気)を伏せた上にのって足を踏み鳴らして踊ります。
こうした健康を祈る御魂鎮めの文化のある「音」の柱を、禰豆子が暴走する遊郭編に割り当てたワニ先生、すごいセンスですよね。
宇髄さんは元忍ということですが(第8巻 70話)、初対面のシーンでは「(伊之助と)同じような次元に住んでる」と善逸から指摘されていたし(第9巻 71話)、もしかすると伊之助と同じように山の文化の修験道に属する人なのかもしれません。
火之迦具土の力と赤い木の実
こんこん小山の子うさぎは
なぁぜにお目々が赤うござる小さい時に母さまが
赤い木の実を食べたゆえ
そーれでお目々が赤うござる
子守唄の2番には「赤い木の実」が出てきますが、これに関して火之迦具土につながる、ちょっと素敵な記事がありました。
参考 文月は、神話の火の神と関わりあり?和風月名「文月」考 |tenki.jp
太陽の勢いが盛んになる真夏は、自然界が「火・産み」「火・膨らむ」季節として、火之迦具土の神話につながると考えることができるみたいです。
軻遇突智の血が染めた、草木や石
上記記事にも出てきますが、日本書紀に出てくる軻遇突智命(カグツチノミコト)は、「一書」の一つにこんなふうに描かれています。
一書曰、伊弉諾尊、斬軻遇突智命、爲五段。此各化成五山祇。一則首、化爲大山祇。二則身中、化爲中山祇。三則手、化爲麓山祇。四則腰、化爲正勝山祇。五則足、化爲䨄山祇。是時、斬血激灑、染於石礫・樹草。此草木沙石自含火之緣也。
是の時、斬りし血(ち)激灑(そそ)いで、石礫(いしむら)樹草(きくさ)に染(そま)る。此の草木(くさき)沙(いさご)石(いは)自(みずから)火(ほ)を含(ふふ)みし緣(よし)也(なり)。
ある書はこう伝えている。伊奘諾尊(イザナギノミコト)は軻遇突智命(カグツチノミコト)を斬り、五つにばらした。これがそれぞれ五つの山祗(やまつみ)に化成した。一つは首で大山祗(おおやまつみ)と成った。二つは体で中山祗(なかやまつみ)と成った。三つは手で麓山祗(はやまつみ)と成った。四つは腰で正勝山祗(まさかやまつみ)と成った。五つは足で䨄山祇(しぎやまつみ)と成った。
この時、斬った血がほとばしり流れ、石や礫、樹や草を染めた。これが草木や砂礫がそれ自体に火を含み燃えるようになった由縁である。
火打ち石といった道具を使うことで、人間は火を起こすことができるのですが、これは「万物に火の霊が宿るからだ」と考えられていたわけですね。
夏は陰陽五行説でいうと、火の要素が割り当てられている季節です。色でいうと、赤で表現される季節です。
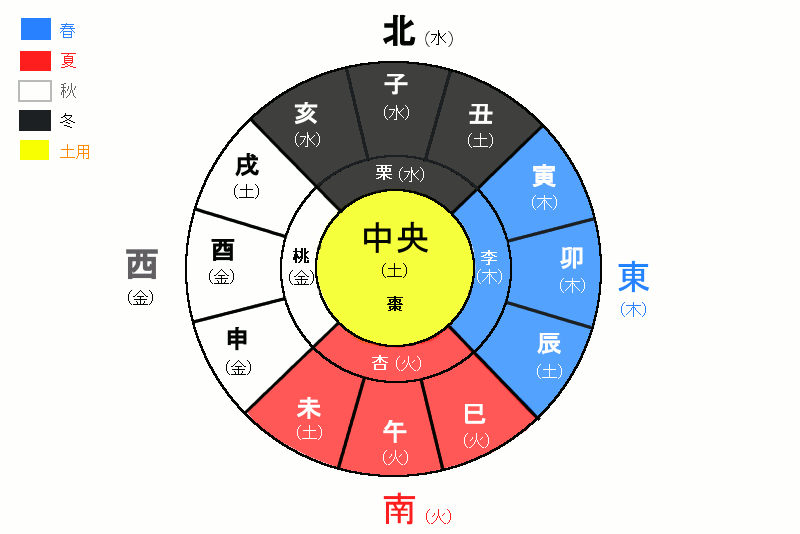
火の要素が強まる夏に、草木が内に秘める火の要素の作用で果実や穀物の実がふくらむのだとしたら、秋に色づく実を食べることは軻遇突智命の力を体に取り入れることになります。
子うさぎの目を赤くした木の実も、もしかすると草木の内に宿る軻遇突智命の火の力を表しているのかもしれませんね。
神話というと、どこか他所の世界の話のような印象がありますが、今食べている食べ物も軻遇突智の伝説につながっていると思えば、身近な話に感じてしまいます。
赤い目をした白うさぎの事情
ただ、赤い目をしたウサギは、赫灼の子につながるかもしれません。
「白い毛のウサギは、赤い目をしているに決まっている」、そう思っていませんか?
昔、小学校で飼っていたウサギが、そんな姿をしていたかもしれませんね。雪が降った日は、南天を目に見立てた雪ウサギを作った人がいるかもしれません。
豪雪地帯に生きるウサギは夏の間は茶色い毛色をしていて、冬になると白い毛に生え変わって「雪ウサギ」と呼ばれるのですが、でも目の色は赤くないのです。実は黒い色のままなんですよ。
目が赤いウサギは、遺伝情報の欠損で生まれるアルビノ種(白変種)です。目の赤いウサギが白い毛をしているのは体の毛に色素がないためで、北国にすむ雪ウサギと違って、季節に関係なく一年中白い色をしています。
昔、小学校などで赤い目をした白ウサギがよく飼われていましたが、これは明治初期に外来種と日本の在来種をかけ合わせたジャニーズホワイトという品種で、アルビノを固定化したものです。
赤い目をしたウサギはどこか身近に感じるけれど、本当は「鬼滅の刃」に出てくる赫灼の子のように、とても珍しい存在ということになるようです。
こうして見ると、炭治郎が禰豆子を鎮めるために歌った子守唄は、物語上の何かのヒントを表しているようで興味深いですよね。
当ブログでは、ウサギや炭治郎の赤みがかった目について、さらに考察した記事があるので、よかったらこちらも覗いてみてくださいね。



